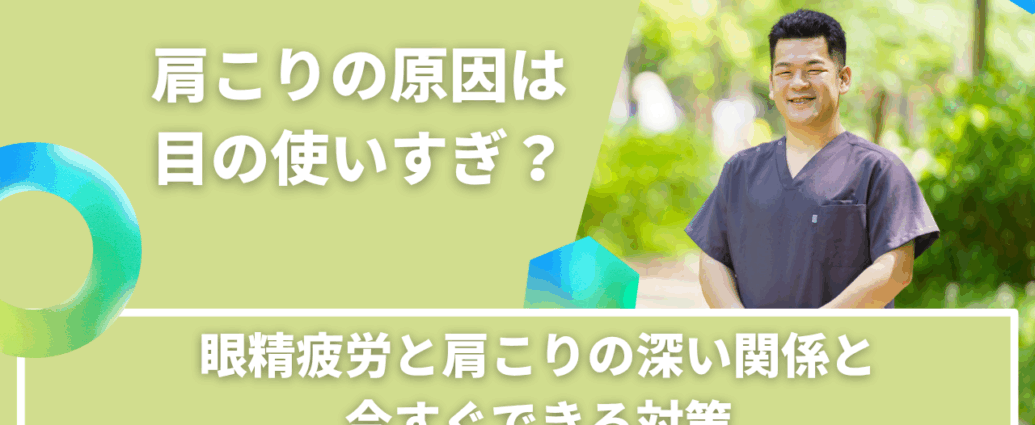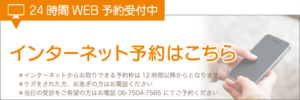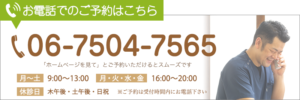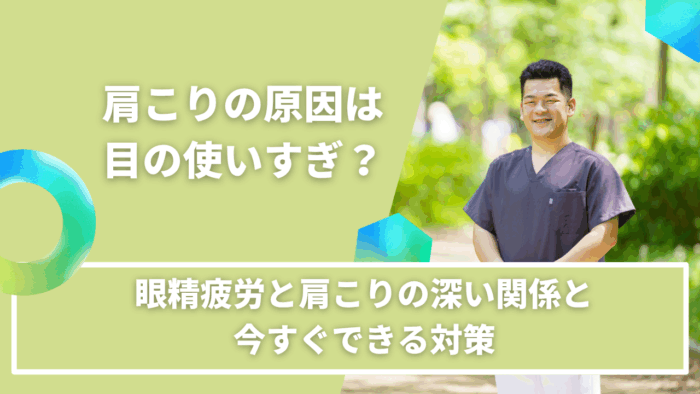
「最近なんとなく疲れが抜けない」
「肩が重だるいだけでなく、目の奥もズーンと痛む」
「視線を変えるとすぐにピントが合いにくい」
このようなことでお困りではありませんか?
体の疲れを感じたとき、目と肩が同時につらくなることがあります。
もしかすると、それは無関係の症状ではなく、実は密接につながっているかもしれません。
スマートフォンやパソコンを長時間使う生活は、今や誰にとっても身近なものになっています。
しかし、その便利さの裏で、目を酷使し続けた結果として、体はさまざまな不調のサインを発しているかもしれません。
そこで今回のブログでは、目の疲れと肩こりの意外な関係性、そして今日からできる対処法や予防法を解説していきます。
最後まで読んでいただけると幸いです。
目次
目がショボショボ、肩がズーン…よくある症状を詳しくチェックしてみましょう。

眼精疲労は、目を長時間使うことによって、視力の調節機能や周辺の筋肉が疲れ、休んでも十分に回復できない状態を指します。
次のような症状がある場合、眼精疲労が関係している可能性があります。
<目の症状>
・目の奥がズーンと重く痛む
・ピントが合いにくい、かすんで見える
・目が乾きやすい、ショボショボする
<体の症状>
・肩や首のこり、張り、重だるさ
・頭がぼんやりして集中できない
・緊張型の頭痛や、時には吐き気
目の不調に加えて、肩まわりに張りや痛みを感じる場合は、「目と肩の連動性」が大きく関係していると考えられます。
なぜ目が疲れると肩までつらくなるの?その意外な関係性とは

「目と肩って場所が離れているのに、なんで一緒に不調が出るん?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
その理由は、主に次の3つになります。
1) 姿勢の乱れによる筋肉の緊張
スマホやパソコンを使う時間が長くなると、目線が下がり自然と前かがみの姿勢になります。
すると、頭を支える首や肩に大きな負担がかかり、筋肉の緊張が生まれます。
この状態が続くと、血の流れが悪くなり、肩こりや首こりが引き起こされやすくなります。
2)一点集中が筋肉に影響
まず一点集中とは、目を動かさずに一つの場所をじっと見つめ続ける状態のことをいいます。
たとえば、スマートフォンの操作では、画面をスクロールしながら視線をあまり動かさずに内容を見続けることが多くあります。
このような状態を続くと、目玉(眼球)を動かす筋肉がこわばりやすくなり、さらに首や肩の筋肉まで緊張して固まりやすくなります。
3)自律神経の乱れ
目の酷使は交感神経を活性化させ、体を常に”緊張モード”にします。
この緊張が続くことで、筋肉が硬直し、コリや痛みを引き起こしやすくなります。
目の疲れと肩こりをやわらげる5つの対処法
つらい不調を和らげるには、毎日のちょっとした工夫が大切です。
無理のない範囲でできるセルフケアをご紹介します。
1)蒸しタオルで目元を温める
温かいタオルを目にあてることで血行が良くなり、目の緊張がほぐれます。
同時に心もリラックスできるので、夜とくに寝る前のリセットタイムにもおすすめです。
市販されているアイケア商品を使うのも便利でいいですね。
2)「20-20-20ルール」を取り入れる
アメリカ眼科学会も推奨するこのルールは、20分作業したら、20秒間、6メートル(20フィート)先を見るというもの。画面に集中しすぎないことで、目の負担を軽減できます。
引用 https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/screen-use-kids
3)気づいたときに姿勢の見直しを行う
デスクワークの場合は、イスの高さや画面の位置、足の置き方を見直し、体に負担のかかりにく姿勢を保ようにしましょう。
たとえば、足先の向きを平行に保つ、膝よりも少し前に足を出して足裏をしっかり床につける、といった位置を意識することが大切です。
気づいたときに姿勢を整えるだけでも、首や肩への負担は大きく変わります。
4) 軽い運動を日常に取り入れる
ウォーキングやラジオ体操のような軽い運動は、血流を改善し、筋肉や神経のバランスを整えるのにや役立ちます。
たとえ1日5分からでも構いませんし、ラジオ体操も好きな動作から始めて大丈夫です。
無理のない範囲で、できることから習慣にしていきましょう。
5)肩や首のストレッチをこまめに行う
肩甲骨を大きく回す、首をゆっくり倒して深呼吸するなど、軽いストレッチを習慣にすることで筋肉のこりを防げます。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回は、眼精疲労と肩こりの深い関係と今すぐできる対策について書かせていただきました。
5つの対処法を参考に、職場やご自宅でご活用ください。
続けていても一向にお困りごとが改善されない場合は、他に原因があるかもしれません。
もし、大阪市東成区周辺でお困りの方がいらっしゃいましたら、当院でご相談いただけたら幸いです。

監修 鍼灸師 柔道整復師 原田 直樹