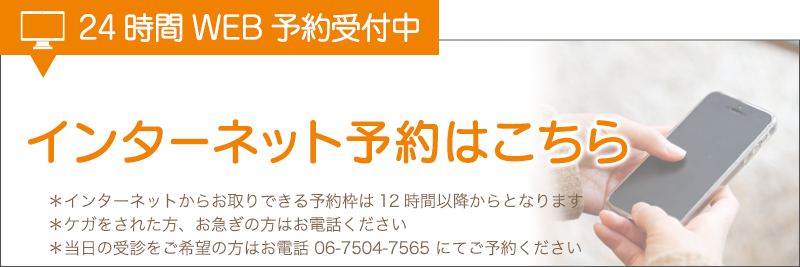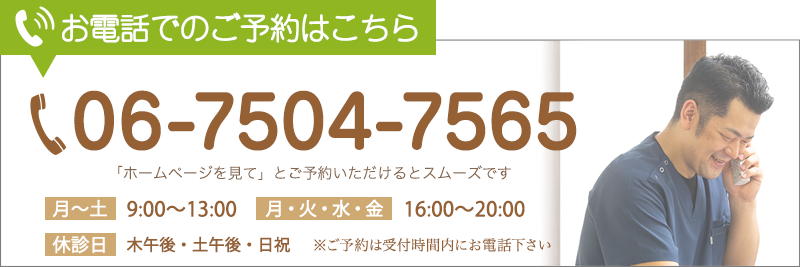Contents
目次
五十肩の原因とは?
肩関節は関節包と呼ばれる袋状の組織に包まれており、内部は関節液というヒアルロン酸を含む液体で満たされています。
関節液は関節の動きを滑らかにする潤滑油の役割と、骨と軟骨がこすれ合う衝撃を防ぐクッションの働きをしています。
これらの組織はもともと弾力性に富んでいますが、加齢とともに筋肉や腱の弾力性が失われると炎症が起こります。
五十肩がもたらす弊害
肩関節は複数の筋肉に囲まれており、腕をスムーズに動かすための重要な役割を担っています。
ところが、肩関節の老化が進むとこれらの筋肉がだんだん硬くなり、組織が炎症を起こすことで「肩や腕を上げる、回す」といった動作が困難となります。
その他にも血行不良や筋肉の柔軟性の低下、こわばりなど様々な悪影響を及ぼします。
どんな人が五十肩になりやすい?
次のような方は五十肩になりやすいといわれています。
- 長時間のデスクワークなどで普段の生活で肩を動かす機会が少ない方
- 偏った身体の使い方により片方の腕ばかりを酷使している方
また、肩こりをはじめ肩の病気といえば女性に多いイメージですが、当院では男性の患者さまにも多くみられます。
診断について
無理のない範囲で腕を挙げていただき、肩の動きを確認します。
肩関節が正常に機能している場合、肩が固定されて腕が挙がりますが、普段から肩や首をすくめてしまう癖のある方は肩ごと腕が挙がってしまいます。
こういった癖を長期間続けていると、肩甲骨を支える筋肉が衰えてしまい肩関節の動きに制限が生じます。
まずは肩関節の動きにフォーカスし、可動域の改善をめざします。
五十肩の症状
五十肩には2つの「時期」があります。
1.炎症期
疼痛、いわゆる「うずき」」がもっとも強く、時には睡眠にも支障をきたすこともあります。
肩に強い痛みがあるこの時期に、ご自身の判断で無理に身体を動かすことは避けましょう。
この「炎症期」に適切な治療を受けておくことが、五十肩の早期治癒のカギとなります。
2.フローズン期(拘縮期こうしゅくき)
炎症期と比べると痛みは軽減されますが、関節が固まってしまうため日常生活動作に不自由を感じることが多くみられます。
- 腕が挙がらない
- 痛みで腕を動かせない
- 一部に痛みが集中する(痛みを感じる場所は個人差があります)
- 高いところに手を伸ばしたときに痛む
関節の拘縮が進行すると、血液の流れが悪くなり修復に時間がかかってしまいます。
当院の五十肩の治療
初回の治療
炎症期を過ぎると肩を動かせなかったことによる関節の拘縮が起こり、関節包が周囲組織と癒着してしまいます。
それに伴い、関節が固まって腕が痛い、動かせないといった問題が生じます。
まずは筋膜リリースを5分間ほど受けていただき、癒着を剥がし肩関節周りの筋肉の柔軟性を取り戻します。
2回目以降の治療
そのため、2、3回目くらいまでは筋膜リリース専用機器を使用して可動域の改善を図ります。
2回目以降は20分間ほど受けていただき、首や背中など、肩以外の部位もアプローチしていきます。
可動域が改善されたら、スタッフの指導のもと肩甲骨の動きを広げる運動やストレッチなどを行なっていただきます。
また、肩以外の部分も動かせるように鎖骨や肩甲骨、胸郭部分にも筋膜リリースを施します。
五十肩と間違われやすい病気
以下の病気は五十肩と混同されやすいため注意が必要です。
腱板断裂(けんばんだんれつ)
インナーマッスルと呼ばれる、肩関節の深部に付着している筋肉(腱板)が損傷・断裂することで生じる病気です。
偏った姿勢などによる身体の歪みが原因であると考えられています。
肩関節が正しい位置からずれることで腱板に負担がかかり、痛みを引き起こします。
石灰沈着(せっかいちんちゃく)
石灰が肩に溜まることで生じる病気ですが、原因は未だに解明されていません。
突然肩に激痛が走り、肩や腕を動かすことができなくなるのが特徴です。
夜間や起床時などに発症しやすいといわれています。
滑液包炎(かつえきほうえん)
肩の内部には滑液包(かつえきほう)と呼ばれる、液体で満たされた袋が介在しており、肩甲骨や上腕骨などの動きを円滑にする役割を果たしています。
この滑液包に摩擦や衝撃など、物理的な刺激が加わって炎症を起こした状態を「滑液包炎」と呼びます。
症状が進行すると五十肩へ発展してしまうこともあります。