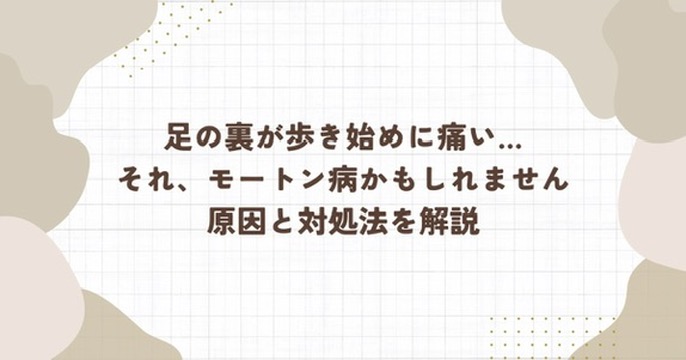
「朝起きて、歩き始めたときにピリッと足裏が痛む」
「靴を履くとき、足指の付け根に違和感」
「足裏の痛みを我慢して歩いていると、痛みが感じなくなる」
このようなことでお困りではありませんか?
朝、ベッドから出て立ち上がった瞬間や買い物の途中でふと立ち止まったとき、
足の指の付け根あたりに刺すような痛みや、ピリピリとしたしびれを感じる…。
でも、しばらく歩いていると治るからと、そのまま放置していることが多い。
これらのお悩みは、「疲れがたまっているだけ」と見過ごされがちな症状ではあります。
実は、”モートン病”という足の神経トラブルが隠れているかもしれません。
今回は、そんなモートン病ってどんなもの?というところから、ご自宅でセルフケアや予防のヒントまで、わかりやすくご紹介していきます。
最後まで読んでいただけると幸いです。
「また気持ちよく歩けるようになりたい」
「行きたいところに行けるようになりたい」
そんな気持ちを大切に、今日からできることを一緒に見つけていきましょう。
目次
モートン病ってどんな病気?
モートン病とは、足の指の間にある神経が、足の構造的な負担や靴の圧迫などによって刺激され、その部分に炎症が起こる病気です。
とくに多く見られるのは、中指と薬指の間です。
モートン病では、足指の先に向かう神経の周辺が腫れ、神経が圧迫・刺激されます。
その結果、足指の付け根から指先にかけて、鋭い痛みや焼けるような痛みが生じます。
発症する確率は女性に多く、男女比は1:4といわれています。
比較的、50代〜60代の女性に多く見られますが、どの年代でも足に負担をかけることで発症する可能性があります。
立ち仕事やよく歩く仕事、また長距離のランニング(マラソンなど)をされている方にも多く見られます。
モートン病が起きやすい原因とは
1)足に合わない靴を履く
つま先が細く、幅が狭いために足の指がギュッと押し込められるような靴や、ヒールの高い靴を長年履いていると、靴の中がまるで、電車のラッシュ時に人がギュウギュウに押し込まれる状態。
その結果、足指の付け根に負担がかかり、神経が圧迫され痛みが出やすくなります。
2)足裏のアーチの崩れ
足裏には、骨や靭帯、筋肉、腱などで構成される、3つの弓状の構造(アーチ)があります。
このアーチ構造によって、足は体重を支えたり、衝撃を吸収するクッションの役割を果たしています。
しかし、この弓状構造が変化が起こると、神経の通り道が狭くなってしまいます。
その結果、歩いているときに神経が圧迫されやすくなり、足への負担が増します。
3)長時間の立ち仕事や歩きすぎ
日常的に立ちっぱなしや歩きっぱなしの生活をしている方は、足の裏にかかる負担が大きくなります。
その影響で、炎症や神経への圧迫が起こりやすくなります。
「よく歩くのは健康にいい」と思っていても、足に合わない靴で長時間歩くことで、逆にトラブルの原因になることもあります。
4)外反母趾や足の変形
外反母趾や、指が曲がってしまう「ハンマートゥ」(つちゆびとも言われます)などの変形があると、足の構造が崩れて、障害部位となる神経への圧力が集中しやすくなります。
こうした足の変形は、靴の影響(サイズがあっていない、紐が緩いなど)や歩き方のクセが関係している場合もあります。
その対処法とは
今回は2つの項目に絞ってお伝えさせていただきます。
1つ目は、「足指ストレッチ」
2つ目は、「膝と足先の向きを合わせる」です。
1)「足指ストレッチ」
足指や足裏を柔らかくすると、足のアーチが本来の働きをしやすくなります。
①足指を床や地面に対して垂直に立てる。
②そのまま床に足を押し付けて、足の甲を伸ばすようなイメージで指を曲げる。
左右交互に3回ずつ行いましょう。
2)「膝と足先の向きを合わせる」
膝と足先の向きをそろえることで、足裏に負担の少ない姿勢をつくりましょう。
〜右足を調節する場合〜
①右足をまっすぐ前に出して、足裏を床につけたままにする。
②そのまま膝を、足先の方向に向けて前に出す。
ポイントは、足指の人差し指と中指の間に向けて膝を誘導する。
③膝を元の位置に戻して、また足先に向けて膝を前に出す。
膝の誘導を5回行いましょう。
※鏡で膝の動きを見ながら行うと、より効果的です。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
今回は、足の裏が歩き始めに痛い…それ、モートン病かもしれません|原因と対処法について書かせていただきました。
「足指ストレッチ」と「膝と足先の向きを合わせる」を参考に、職場やご自宅でご活用ください。
続けていても一向にお困りごとが改善されない場合は、他に原因があるかもしれません。
その際は、お早めに近隣の専門機関にご相談されることをおすすめします。
もし、大阪市東成区周辺でお困りの方がいらっしゃいましたら、当院でご相談いただけたら幸いです。
監修 鍼灸師 柔道整復師 原田 直樹
